 MariaDBは、主要なLinuxディストリビューションで採用されているデータベースです。
MariaDBは、主要なLinuxディストリビューションで採用されているデータベースです。
少しご存じの方であれば、Linuxに採用されているデータベースと言えばMySQLやPostgreSQLを思い浮かべるかもしれませんね。
MariaDBは、MySQLから派生したもので、MySQLと共通点の多いデータベースです。
そして、MariaDBは、現在最も勢いのあるデータベースの一つであると言えます。
今回は、MariaDBについて、その概要や強み、将来性について解説します。

2020.08.27
MySQLとは。特徴や強み、無償版と有償版の選び方を解説!
MySQLは、Oracleなどと同じように世界中で幅広く利用されているデータベースです。「大量の情報を高速で扱える」、「耐障害性が高...
MariaDBの利用なら
Winserverの共用サーバー!
\ 2週間無料・丁寧な電話サポート/
Windows 共用サーバーを使ってみる
目次
MariaDBって?
MariaDBはどのようなデータベースなのでしょうか。
データベースについて基本的なおさらいを含めて解説します。
データベースの種類
データベースには、データの格納の方式によっていくつかの種類があります。
階層型:データをツリー状に格納
階層型データベース(=階層型データモデル)は、データが階層のように構成される、ツリー構想(木構造)を取っています。
一つの親データ(ノード)に対して、複数の子データ(ノード)が存在し、親と子は下図のように「1対多」の関係となります。

階層型データベースを、会社の組織図で例えて説明します。
社長の下には「情報部」「経理部」「総務部」などの部署があり、各部署の下にはより細かな分類として、業務ごとに分類された課が存在します。

この会社に、AさんとBさんという2名の社員がおり、この2名を階層型データベースで構成された社員名簿に登録する必要があるとします。
Aさんは人事課のみに所属するため、人事課に登録します。
Bさんは人事課と法務課を兼務しているため、それぞれの課に登録します。
つまり、Bさんは重複登録されることになります。
このような重複登録を行うのはデータとして不自然なため、この点が階層型データベースのデメリットと言えるでしょう。

階層型のメリットは、1つのデータを探す手順が限定されるため、速度が非常に速いという点です。
一方で、データの追加や削除を行った場合、ルートの再登録が必要となるなど、柔軟性が低いというデメリットがあります。
ネットワーク型:データを網目状に構成
ネットワーク型データベースは、階層型と異なり、1つの子データ(ノード)から複数の親データ(ノード)へのアクセスが可能です。
これらのノードの繋がりが網目上になることから、ネットワーク型と呼ばれています。
複数の課に所属する人物がいた場合においても、ネットワーク型であれば、該当人物を重複登録する必要はなくなり、階層型で課題となっていた冗長性を排除する仕組みとなっています。
しかし、階層型と同様にプログラムがデータ構造に依存してしまうため、「データの柔軟性」については高くないと言えるでしょう。
リレーショナル型:データを表形式にして格納
リレーショナル型とは、データを行と列からなる表形式にして保管するものです。
SQLと呼ばれるデータベース言語を利用して、複雑なデータを操作できるため、非常に幅広く利用されています。
このリレーショナル型のデータベースを管理する仕組みを「リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)」と呼びます。
この中で現在もっとも幅広く利用されているのがリレーショナル型データベース(RDB)で、代表的なものにOracleやMySQLなどがあります。
今回取り上げているMariaDBもRDBです。

2020.08.13
Oracleとは。データベースの特徴や強みなど、人気の理由を解説
Oracle(=オラクル)といえば、一般的にはOracle社が開発・リリースしているOracle Databaseのことを指します。 ...

MariaDBとは
MariaDBは、MySQLの派生版として誕生したデータベースで、元々MySQL5.5をベースにして開発が進められたものです。
現在のMariaDBでは、ここに以下のような独自機能が追加されています。
- レプリケーションの並列処理による性能向上
- 複数マスターによるレプリケーション
- グローバルトランザクションIDの採用によるサー切り替え
など
これら以外にも権限管理の効率化などMySQLには含まれていなかった多くの機能が追加されています。
MySQLとの違い
MariaDBは、元々MySQLの派生として開発されたものと説明しましたが、具体的にどういった違いがあるのでしょうか。
ここで改めて整理しておきましょう。
| MariaDB | MySQL | |
|---|---|---|
| ライセンス | オープンソース | オープンソース |
| 管理 | コミュニティによる管理 | Oracle社によるベンダー管理 |
| シェア | Linuxディストリビューションでの 採用など急速に伸びている | 非常に高い |
| セキュリティ (暗号化機能) | 暗号化の対象が多い | 暗号化は限られている |
| パフォーマンス | 高い | MariaDBには劣る |
| 堅牢性 | 高い | 普通 |
| クラスター構成 | 対応 | 非対応 |

MariaDBの特徴や強みとは
MySQLの派生版であるMariaDBはどういった特徴のあるデータベースなのでしょうか。
また、どういった強みがあるのでしょうか。
MySQLやMicrosoft SQL Serverについては、こちらで詳しく説明しています。

2020.08.27
MySQLとは。特徴や強み、無償版と有償版の選び方を解説!
MySQLは、Oracleなどと同じように世界中で幅広く利用されているデータベースです。「大量の情報を高速で扱える」、「耐障害性が高...
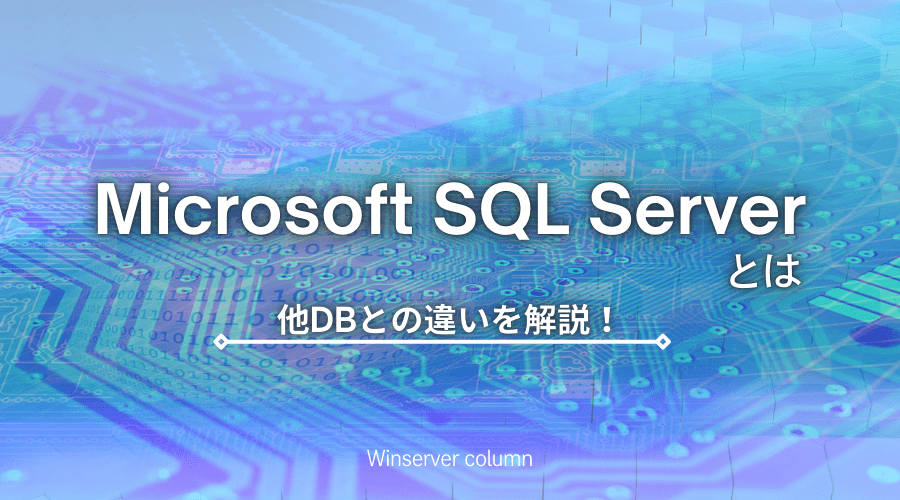
2020.02.06
Microsoft SQL Serverとは。他DBとの違いを解説!
SQL Serverは、Microsoftが開発、リリースしているデータベース製品です。Windows OSとの相性が良いため、Wi...
他のDBとの比較
MariaDBの特徴を理解するために、先に比較したMySQL以外の主なRDBと比較してみましょう。
| MariaDB | PostgreSQL | Oracle | |
|---|---|---|---|
| ライセンス | オープンソース | オープンソース | 有償 |
| サポート体制 | それほどない | それほどない | 充実 |
| プラットフォーム | 幅広く使える | 幅広く使える | Windows、Linux等 |
| クラスター構成 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 機能 | あまり複雑な処理はできない | ある程度複雑な処理も可能 | 複雑な処理も可能 |
| 堅牢性 | 高い | 高い | 高い |
MariaDBの強みや得意分野とは
他のDBとの比較結果を踏まえると、MariaDBの強みは以下のようなものであると言えます。
- オープンソースなので無償で使える
- 目的に合わせて幅広いOSを選択できる
- クラスタ構成に対応しており、大規模な処理を行えるようになっている
また、他にも「ロードバランサーによる負荷分散機能が使える」「多機能である」ことや、「MySQLからの手軽な移行」が可能といったこともMariaDBの強みです。
こうした特徴を備えたMariaDBは、標準のRDBとして、さまざまなLinuxディストリビューションに搭載されています。
クラスタ構成や負荷分散機能などによってエンタープライズ市場でも利用可能なデータベースとなっています。
MariaDBとエンタープライズ利用
MariaDBは、エンタープライズ市場でも利用が広がっており、強みを発揮しています。
こうしたエンタープライズ市場でのMariaDBの現状について取り上げます。
エンタープライズ市場で求められるポイント
まずは、エンタープライズ市場で製品が採用される場合、どのような点が重視されるのか見ておきましょう。
IT関連製品に限らずエンタープライズ市場に求められるポイントは、大きく以下の4つです。
- 機能や性能、価格が要件に合っていること
- 拡張性や信頼性は十分か
- セキュリティについて問題はないか
- サポート体制は整っているか
次の項では、MariaDBがこうした要素についてどのように押さえているのか解説します。
エンタープライズ市場向けサービス「MariaDB Enterprise」
MariaDBは、2019年2月にエンタープライズ市場向けの製品である「MariaDB Enterprise Server」を発表しました。
これを含むエンタープライズ向けのサービスとして、MariaDB Enterpriseと呼ばれるものが、サブスクリプションサービスとして提供されています。
このサービスには、通常のMariaDBと比べて、以下のような特徴があります。
- 商用にカスタマイズされている(高性能、高可用性)
- 開発、保守などを行うツールが提供されている
- 24時間365日の専門的なサポート体制が使える
- コンサルティングサービスが提供されている
など
MariaDBは、エンタープライズ市場へもサービスを拡大しており、将来性が期待できます。

MariaDBの将来性とは
ビッグデータなど、これからデータベースの重要性が増すことは確実です。
インターネット上の膨大なデータを適切に格納し分析等の処理を行うために高性能なデータベースの役割は今まで以上に重要になります。
そうした中で、MariaDBは、AWS(Amazon Web Services)やGCP(Google Cloud Platform)など大手のクラウドサービスでも利用できるようになっているなど、これからのクラウド時代にも対応できるようになっています。
また2018年には、ビッグデータ分析スタートアップであるMammothDBを買収するなど、ビッグデータ分析についての強化も進めており、将来に対してのサービス強化を期待できる状況にあります。
先ほど解説したMariaDBの特徴にも、堅牢性の向上などと併せてクラスタ構成への対応が含まれており、エンタープライズ向けのMariaDB Enterpriseではさらに強化されています。
こうしたMariaDBのRDBとしての性能の強化は、これからのデータベースの重要性が増す時代のニーズにもよくマッチしたものとなっています。
ビッグデータについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

2020.07.16
ビッグデータとは。定義や活用例をご紹介。AIとの関係性は?
「ビッグデータ」という言葉、皆さんもいろいろなところで聞くことが多いのではないでしょうか。インターネット上でのSNSへの投稿情報、検...
クラウドサービスについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

2021.08.05
クラウドとは。インターネットサービスの種類や活用方法を解説。
私たちの生活に欠かせないものとなったクラウド。クラウドは、導入や運用のコストが安く、手軽に使えるため、大企業から中小企業、個人に至る...
まとめ
MariaDBは、MySQLから派生し、Redhatをはじめとする多くのLinuxディストリビューションで標準のデータベースとして採用されています。
MariaDBは、「堅牢性の向上」「クラスタ構成への対応」「高速化」など、MySQLに比べてエンタープライズ市場でも受け入れられるようなさまざまな追加機能を備えています。
さらに、「充実したサポート体制」などを備えたエンタープライズ市場向けのMariaDB Enterpriseサービスも提供されています。
そして、AWSなどのクラウドサービスでもMariaDBは利用できるようになっています。
将来性ということであれば、クラウドだけでなくビッグデータなどデータベースが活用される領域でもMySQLにはない独自機能によって対応ができるようになっています。
このように、MariaDBは、将来にわたって利用され続けることが期待できるデータベースと言えるでしょう。
Webサイトやブログを始めるならWinserver!
Winserverは、Windowsサーバー専門のレンタルサーバーです。
20年以上の運用実績の中で、個人の方から法人の方まで、幅広いお客様が快適にご利用いただけるサービスを提供してきました。
Winserverの共用サーバーは、Webサイトやブログを始めたい方におすすめです。
ホームページの公開やメールアドレスの作成などのサーバーの設定から、サーバーの保守管理やメンテナンス等を全てWinserverが対応いたします。
また、WordPressやEC-CUBEなど、人気のCMSをコントロールパネル上から簡単にインストールすることできます。
共用サーバーは専門的な知識が不要で、初心者の方も手軽に利用することができます。
2週間無料トライアルも行っているため、まずはお気軽にお試しください。
こちらから、共用サーバーの紹介資料をダウンロードできます。

共用サーバー紹介資料
ホームページやブログを公開するために最適な共用サーバーの概要、特徴、料金プランをまとめた資料です。
「WordPress専用プラン」についても紹介しています。

共用サーバー紹介資料
ホームページやブログを公開するために最適な共用サーバーの概要、特徴、料金プランをまとめた資料です。
「WordPress専用プラン」についても紹介しています。



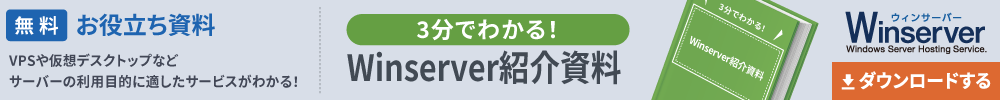










コメント