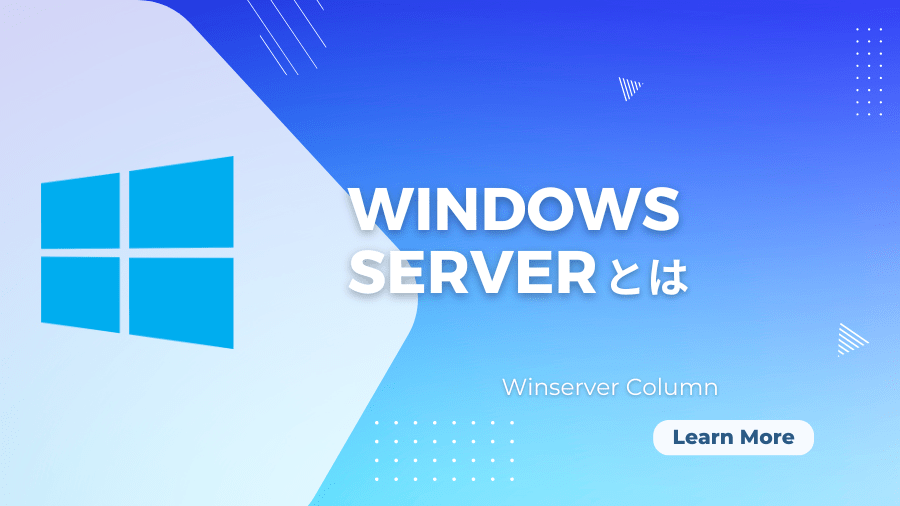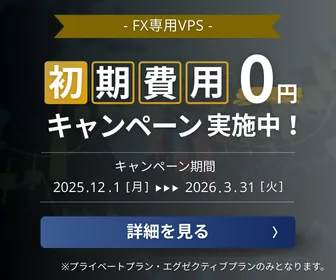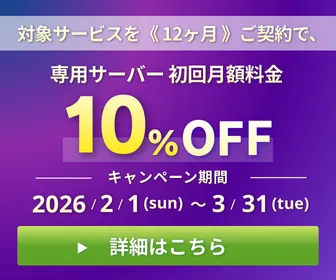この記事の信頼性:本記事は、Windows Serverを20年以上提供している「Winserver」のマーケティングチームおよび技術チームが執筆しています。実際に企業ユーザーから寄せられた設定相談やサポート事例に基づき、初心者にもわかりやすく解説しています。最終更新日:2025年7月10日

マイクロソフト社のライセンス改定に伴い、2025年10月1日以降、AWS、Azure、GCPなど「Listed Provider」上でのSPLAライセンス持ち込みが禁止されることになりました。
これに伴い、自社で契約しているクラウドサービス上でMicrosoft製品(例Windows ServerやOffice)を利用している企業は運用体制の見直しが必要になる可能性があります。
本記事では、長年クラウドやホスティングに携わってきた筆者が、SPLAの基本的な仕組みと改定内容の要点をわかりやすく解説します。
さらに、想定される影響や具体的な対策・移行プランについてもご紹介します。
対象読者:SPLAライセンス改定の影響でMicrosoft製品の運用に不安を抱える情報システム担当者の方
\ 2週間無料でお試しできます! /
 ・Windows Server OSのVPSが月額2,035円~!
・Windows Server OSのVPSが月額2,035円~!
・全プランSSD搭載!
・丁寧な電話サポート!
Windows VPSを使ってみる
目次
SPLAとは
概要
SPLA(スプラ/Services Provider License Agreement)は、マイクロソフトが提供するライセンスプログラムの一つで、サービスプロバイダーがマイクロソフト製品を月額課金で顧客に提供するための仕組みとなっています。
サービスプロバイダーとは、ホスティング事業者、データセンター事業者、クラウドプロバイダー(SaaS)などの業者を指します。
通常のボリュームライセンスとは異なり「自社利用」ではなく「第三者へのサービス提供」が目的のライセンスで、対象サービスはPCレンタル、ホスティング、クラウドサービス、RDP接続、VPS、VDIなどが該当します。
従来は、サービスプロバイダーが他社のデータセンター上に構築した仮想マシンにもSPLAを適用できる柔軟な仕組みが許容されていました。
しかし、今回のライセンス改定により、この適用範囲に厳しい制限が設けられる点が最も重要な変更点と言えるでしょう。
SPLAの特徴とメリット
マルチテナント環境に最適
SPLAはホスティングやIaaS、SaaS、DaaSなど、さまざまな形態でのサービス提供が可能です。
データセンターでのマルチテナント構成にも適しています。
柔軟なコスト管理
使用量に応じて月額で課金されるため、ユーザー数やインスタンス数の増減に合わせてコスト最適化が可能です。
常に最新バージョンを利用可能
SPLAライセンスには、ソフトウェアの常時アップグレード権限が付帯しています。
これは、ボリュームライセンス契約で得られるSoftware Assurance(SA)と同等のメリットを提供します。
初期投資の抑制
ライセンスは提供した分だけ支払う従量課金制のため、初期費用を抑えられます。
マイクロソフト公式サイトでも、「お支払いいただくのは、毎月にエンドユーザー様に提供したソフトウェア サービスをベースとしたライセンス料のみです。初期コストはかからず、月ごとの販売ノルマや長期的なコミットメントもありません。」と説明されています。
マイクロソフト公式サイト:サービス プロバイダー様向けライセンス プログラム
SPLAの主な対象製品
SPLAが適用できる代表的な製品は、以下の通りです。
・Microsoft Windows Server(含RDSライセンス)
・Microsoft Office
・Microsoft SQL Server
など
これらは多くのクラウドベンダーやホスティング事業者で利用されている主力製品であり、今後のライセンス方針変更により導入方針の見直しが必要になる場面も増えると想定されます。
\ 2週間無料でお試しできます! /
Windows VPSを使ってみる
SPLAライセンスの改定とその影響
SPLAライセンス改定の背景とマイクロソフトの狙い
今回のSPLA規約改定は、マイクロソフト社が2022年10月1日付で公式に発表したものです。
以下の公式ブログ記事にて「SPLA program update regarding outsourcing」として詳細が紹介されています。
Microsoft Partner Blog :New licensing benefits make bringing workloads and licenses to partners’ clouds easier
日本語要約:
「ホスティング事業者のエコシステムを促進し、従来のアウトソーサーやデータセンター事業者に恩恵を与えるため、Listed Provider のデータセンターでSPLAライセンスを第三者提供する機能を削除する。影響を受ける事業者は、2025年9月30日までに、Listed Providerから移行するか、直接ライセンスを取得する必要がある」
Listed Providerとは、Microsoftが指定したクラウド事業者でAlibaba Cloud、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azureの4社のことを指します。
つまり、2025年9月末日をもって、AWS、Azure、GCP、Alibaba環境で、事業者がSPLAライセンスの持ち込みが禁止されることになります。
改定による影響(サービス提供事業者側)
事業者は、データセンターのAWSやGCPといった基盤上でSPLAのサービス提供ができなくなります。
この変更によって、事業者が受ける主な影響は以下の通りです。
・エンドユーザーへのSPLAサービス提供の終了
・ライセンス提供モデルの切り替え
(SPLA→Listed Provider直接、SAのライセンスモビリティなど)
など
事業者は、今後の提供形態や契約モデルについて早急な検討が必要です。
改定による影響(SPLAを利用している企業ユーザー側)
SPLAライセンスの制限は、利用企業にとっても他人事ではありません。
以下のような影響が想定されます。
利用者側への影響例
・利用中のサービスが継続不可となる可能性
⇒提供事業者のSPLA終了により、マイクロソフト製品の利用が停止されるケース
・コストの上昇
⇒安価だったライセンス提供が終了し、正規購入への切り替えを求められる・運用不可の増大
⇒自社管理ライセンスや直接契約への移行により、IT部門の業務が増える
特に、Windows ServerやOffice、SQL ServerをSPLA経由で利用していた企業は注意が必要です。
利用停止リスクに加え、コスト上昇や運用管理の複雑化といった課題に直面するおそれがあります。
SPLAライセンスを利用しているかの確認ポイント
対策を検討する前に、利用中のマイクロソフト製品のライセンスがSPLAに該当するかどうかを確認しましょう。
確認ポイント①:ライセンス保有状況の確認
・マイクロソフト製品のライセンスを自社で購入し保有している
→基本的にSPLAの影響なし
・自社でライセンスを購入していないが、マイクロソフト製品を利用中
→SPLAの可能性あり、要確認
Office ,Windows Server,SQL Server,RDSなどを契約事業者経由で使っているが自社でライセンスを持っていないという場合は、続いて以下を確認してください。
確認ポイント②:契約している事業者の確認
・Listed Providerのクラウド業者(AWSやAzure)から直接ライセンス付プランを契約している(例:EC2のライセンス込み)
→SPLAではない
・Listed Provider以外のクラウド、ホスティング事業者と契約している
→SPLAの可能性あり
例えば、AWS EC2のWindowsライセンス付き仮想マシンなど、Listed Provider自身が提供するモデルは今回排除されるSPLAに該当しません。
一方で、事業者のホスティングサービスで月額払いにてマイクロソフト製品を使っている場合は、SPLAで提供されている可能性が高いため、提供元事業者へ早急に10月以降の提供方針を確認することをおすすめします。
\ 2週間無料でお試しできます! /
Windows VPSを使ってみる
SPLA利用終了に備えた対応策と移行シナリオ
SPLAが2025年10月以降利用できなくなる場合に備え、以下の4つの選択肢があります。
Listed Providerのライセンス提供モデルに切り替え
Listed Provider自身が提供するプラン(例:AWS EC2の場合Amazon WorkSpacesなど)に乗り換えるケースです。
・メリット:自社でライセンス管理をしなくてよい
・デメリット:クラウドサーバー(IaaS)の構築、運用知識と工数が必要。長期的に見て運用コスト増加の可能性あり。
・ポイント解説:IT管理リソースに余裕があり、既にAWSやAzureの管理経験がある企業にとっては、比較的スムーズな移行ルートといえます。
SAライセンスモビリティを利用したBYOLへ移行
自社でライセンスを持ち、SAの特典としてListed Providerの基盤上でマイクロソフト製品を持ち込む方法です。
・メリット: 現行クラウド環境を変更せず維持できる
・デメリット: ライセンスコストが高くなる傾向。持ち込み条件は事業者ごとに異なり、確認・管理が複雑。
・実務補足:BYOLを検討する際は、マイクロソフトの「ライセンスモビリティ利用規約」および各クラウド事業者の対応状況を事前に確認しておくことが重要です。
オンプレミス環境へ移行(自社運用)
クラウドからオンプレミスへ回帰し、自社で物理サーバーに切り替える方法です。
・メリット:ライセンス構成やインフラ設計の自由度が高い。長期的に自立運用が可能。
・デメリット:移行コスト、初期投資、保守運用コストの負担。
SPLA継続可能なホスティング事業者への移行
Listed Provider以外のホスティングサービス事業者であれば、今後もSPLAを使い続けることが可能です。
現在の使用環境に近い形での移行ができるため、大きな構成変更を避けたい企業に適した選択肢といえます。
・メリット: 従来通りの月額課金で利用可能。ライセンス管理不要。
・デメリット: 事業者の選定に時間がかかる
・信頼できる選び方:SPLA対応が明示されている実績あるホスティング事業者を選び、「2025年10月以降も提供継続の方針があるか」を確認するのが重要です。
現状のアクションプラン
マイクロソフトによるSPLAライセンスの改定は、一見すると一部の事業者に限定された話のように見えますが、実は多くの企業に影響を及ぼす重要な変更です。
以下では、既にSPLA環境を利用している方・これからクラウド導入を検討している方それぞれに向けた、現実的な対応策を解説します。
既にサービスを利用中の方へ:今すぐの棚卸しと比較検討を
2章を参考にSPLAライセンスを利用しているかを確認のうえ、もし10月以降影響が出るようであれば、早めに対策を検討しましょう。
影響の見積りと、サービスを他環境や他業者に移行するのであれば、複数の移行プランについてコストやリスク等を比較していくことが必要です。
専門のコンサル、パートナーへの相談や、トライアルサービスがあれば申込み、スモールスタートで移行の検証・評価を実施することも有効です。
今後クラウドサーバー等の利用を検討している方へ:選定段階からの見極めがカギ
SPLAライセンス改定の件を考慮し業者を選定するのがよいでしょう。
SPLAが継続して使えるホスティング事業者が安心といえます。
「クラウド」だけにこだわらず、VPSや共用サーバーといったレンタルサーバー形態も候補に含め、用途に応じて柔軟に比較検討することをおすすめします。
信頼できるSPLAパートナーとして:Winserverのご紹介
Microsoft認定のホスティングパートナーWinserverは、10月以降もこれまで通りSPLAが使えるサービスの1つです。
幅広い用途に使えるVPSや共用サーバーで、OfficeやSQL Serverといったマイクロソフト製品を月額課金制で利用でき、SPLAのライセンス制限を確実に回避できます。
よりカスタマイズの自由度が高い専用サーバー、プライベートクラウドプランも用意しています。
\ 2週間無料でお試しできます! /
Windows VPSを使ってみる
社内に詳しい技術者がいないという場合も、導入や構築、運用を代行するマネージドサービスがあります。
サーバー移行から環境構築まで幅広く対応可能で、用途に応じた最適なプランを提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
\ クラウド環境への移行・構築運用のお悩みを解決 /
クラウドマネージドサービスをみる
まとめ
本記事では、マイクロソフトのSPLAライセンス改定に伴う影響と、現実的な対応策について解説しました。
この記事でSPLAという言葉を初めて知った方も多いと思います。
このライセンス改定は大きく報道されてはいませんが、多くの業者がAWSやGCPといったListed Providerの基盤でサービスを展開しているのは確かですので、クラウドやホスティングサービスを契約している企業にとっては注視すべき問題といえるでしょう。
マイクロソフトの複雑なライセンス形態のなかで、いかにイニシャル・ランニングコストを抑えていくことができるか、自社の現状を棚卸ししたうえで最適な運用を検討する一助となれば幸いです。
参考リンク
※この記事は2025年7月時点の情報に基づいて執筆されています。掲載内容は将来的に変更される可能性があります。
※本記事の情報は、各ソフトウェアの公式サイトおよび開発元のドキュメントに基づいて作成しています。
最終更新日:2025年7月10日
この記事の執筆者について:
本記事は、Windows専門レンタルサーバーを20年以上提供する「Winserver(株式会社アシストアップ)」が運営する公式コラムです。
当社はMicrosoft SPLAパートナーとして、法人・個人を問わず多数の顧客に対し、Windows Server環境の導入・運用支援を行ってまいりました。
執筆・構成は、技術サポートとマーケティングチームが共同で担当。実際に社内導入やお客様からのフィードバックに基づいた情報をもとに執筆しています。
クラウドマネージドならWinserverにお任せ
Winserverのクラウドマネージド
Winserverのクラウドマネージドは、請求代行・初期構築・運用まで様々な面でサポートさせていただきます。
ホスティング事業を20年以上運用する中で培ったインフラエンジニアの知見を活かして、クラウド環境への移行・構築運用のお悩みを解決します。
請求代行サービス
クラウドサービスを利用する際、気を付けなければいけないのが支払い条件です。
クラウドサービスの請求は、ドル建て、クレジットカード決済が多く、会社のルールによっては導入できない場合があります。
Winserverのクラウドマネージドでは支払い関連のお悩みを請求代行サービスで解決いたします。
Winserverで支払いを代行することで円建てでの請求書発行、支払いが可能となります。
構築運用サービス
クラウド環境の構築・運用・保守をサポートするサービスです。
データの移行、テレワーク環境構築、監視・運用代行のサービスや現在利用中のクラウドサービスを最適化するコンサルティングサービスなど、多岐にわたりクラウド環境をサポートいたします。
まずはWinserverにご相談ください
担当者とのお打合せをご希望の場合はこちら
Winserverでは、お客様一人ひとりにあわせて最適なサービスプランをご提案いたします。
「AWSと専用サーバーのどちらが良いか迷っている」「マネージドの依頼範囲を相談したい」など、担当者とのお打合せを希望される場合は、オンライン個別相談会にお申込みください。
お見積のご依頼、構成のご相談はこちら
お見積のご依頼やその他構成などのご相談は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
最大1営業日以内にご返信いたします。
メールや電話によるサポートが充実しており、サーバーを初めてご利用の方の疑問にも専門のスタッフが丁寧にお答えします。
お電話でのお問い合わせ:0120‐951‐168
【 平日 】9:00~12:00 / 13:00~17:00

クラウドマネージド紹介資料
クラウドマネージドは、クラウドの初期構築や運用を、Winserverが代行するサービスです。
お客様のご要望に合わせて、クラウド導入における様々な課題の解決を支援します。
本資料では、サービス内容、ご依頼いただくメリット、対応例をご紹介しています。

クラウドマネージド紹介資料
クラウドマネージドは、クラウドの初期構築や運用を、Winserverが代行するサービスです。
お客様のご要望に合わせて、クラウド導入における様々な課題の解決を支援します。
本資料では、サービス内容、ご依頼いただくメリット、対応例をご紹介しています。